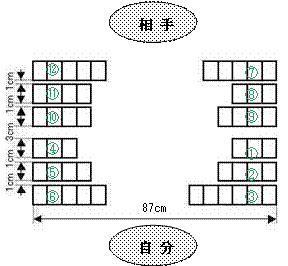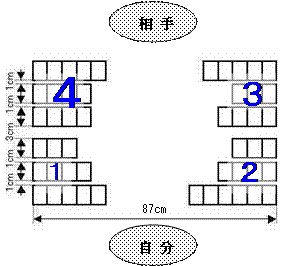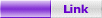 全日本かるた協会
全日本かるた協会
三重県かるた協会指導指針 戻る
2006.11.3
[はじめに]
1.札の配置
2.札の暗記(暗記時間中)
3.札の暗記(試合中)
4.読みの聞き方・札の取り方
5.分れ札の処理
6.送り札
7.試合運び
[はじめに]
本資料は、競技かるたのB級、C級、D級で常に上位入賞できるレベルに必要な基本的な技能について、
三重県かるた協会の先輩諸氏から伝授されてきた内容を中心に記述したものである。
<大原則>
1.相手に、実力を出させないような札の配置、送り札の選定、試合運びをする。
2.相手陣を攻める(特に相手陣の右)。
【なぜ「攻め」なのか】
理由1)かるたの作戦は8〜9割が送り札。送り札により、自分が取りやすく、相手が取りにくい体制をつくる。
そのためには、相手陣を取る必要がある。
理由2)仮に完璧に守ったとしても、自陣が相手よりも先に無くなる確率は5割。安定して勝つためには、相手陣も取らないとダメ。
理由3)相手陣の右を攻めた方がトータルで取れる確率が高い。
(一旦自陣を守って相手陣を取る確率よりも、まず攻めて自陣に戻ってくる方が払い手の速さもあって取れる確率が高い。
また、相手陣の右を攻めると相手陣の左が出ても対応できるが、その逆は難しい。)
理由4)一般的に相手陣の右は相手の守備の中心で、枚数はもとより重要な札も多くある。
そこを取ることで対戦相手に精神的なダメージを与え、試合も優位に進められる。
※ 以下は、前出の大原則に基づいている。
1.札の配置
自身には取り易く、対戦相手にはできる限り取りにくい配列を目指す。
◆原則として「む、す、め、ふ、さ、ほ、せ」、「う、つ、し、も、ゆ」は下段。
◆(右利きの場合)大山札は右の中段もしくは下段の外側(囲い手で取る)。
◆三重県かるた協会では、共札は左右に分けることを推奨。
◆(右利きの場合)左右をバランスさせる。気持ち、左より右が多くなるように。
◆各段の最大枚数は6枚を目安とする
◆分れ札の場合は、原則として対角線の中段もしくは下段に配置(上段にはおかない)。
“縦”の分れに配置する場合は、出来る限り自陣の札を相手よりも外側へ。
◆三重県かるた協会では、上段・中央への配置は推奨していない。
2.札の暗記(暗記時間中)
◆各段単位で繰り返し覚える。(目を瞑っても言えるようにする。)
◆①自陣右上段→②自陣右中段→③自陣右下段→④自陣左上段→⑤自陣左中段
→⑥自陣左下段→⑦相手陣左下段→⑧相手陣左中段→ ⑨相手陣左上段
→⑩相手陣右上段→⑪相手陣右中段→⑫相手陣右下段の順に覚える。
◆その過程で第一音の同じ札が出てきたら、前に出てきた札を復習する。
◆一通り覚えたら、第一音が同じ札のりに行く順をシミュレーションする。
「あ」札からやると効果的。
また、可能であれば半音での意識付けをここでやるとさらに効果的。
◆原則として、第一音の同じ札が相手陣と自陣にある場合は相手陣の札を、
また、相手陣で左右に第一音が同じ札がある場合、
相手陣右から取りにいくように意識付ける。
◆時間配分は、自陣4〜5分、相手陣7〜8分、シミュレーション2〜3分。
※自陣は、並べた瞬間に頭に入るようになるのが理想。 |
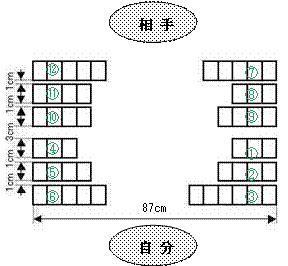 |
3.札の暗記(試合中)
◆試合の序盤、あるいは拮抗している展開での中盤までの暗記の比率は、
相手陣右、相手陣左、自陣右、自陣左の順に、概ね4:3:2:1程度。
◆覚え方は、15分の暗記と同様に順番に覚えるやり方とシミュレーションの
併用。また、読まれた札と同じ第1音の札を復習する。
◆自陣は、単独札(第1音がその札しかない場合)、移動した札、
送られてきた札、決まり字が変化した札が中心。
◆自陣は、試合の序盤や拮抗した展開ではあえて守る必要はないが、相手の
手が甘かったり、相手が抜けていたりした場合は拾える程度の暗記は必要。
◆送った札、送られた札及びその周辺の札は特に注意。
(移動した直後のみならず、2〜3枚あとまで確認する。) |
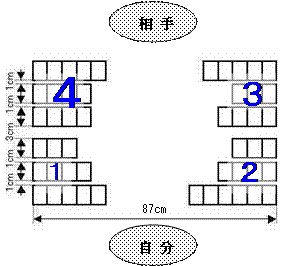 |
4.読みの聞き方・札の取り方
1)読みの聞き方
◆余韻に入ったら、相手陣左下段から右下段の順で最終確認し、相手陣右下段を取りにいけるように構える。
◆「間」の間は全神経を読み手の第1音を聞くことに集中し、第1音を聞くと同時に暗記中のシミュレーションに従い手を動かす。
◆「ねらい」過ぎると第1音を聞けないので注意する。
2)札の取り方
◆出札を直接払うことを心がける。払う瞬間は、出札の位置、それに対して自分の手がどこから入ったか、
相手の手がどこから来たかが分かるように心がける。
◆決まり字が読まれるタイミングで札を払えるようにスタート、スピードを調整する(札の上で止まると、スピードロスとなる)。
◆大山札は囲い手で取る。
◆上段中央の札は突き手で取る。
◆1−1は自陣の札を守る。
5.分れ札の処理
◆最初の暗記時間中12〜13分は両方とも覚える。
◆暗記時間中ラスト2〜3分のシミュレーションの段階及び試合中は、相手陣にある方のみを覚え
(特に決まり字にアクセントをつけて覚える。)、自陣にある方は覚えない。
◆相手陣の札であれば取り、違っていれば自陣に戻る。
※理想的な分れ札の処理は、双方の札を覚えてキッチリ聞き分けて取ることだが、最初は難しい。
実力のアップとともに徐々に切り替えていくとよい。
◆特に両者が10枚を切って拮抗している局面では、分れ札が勝負札になってくるので、暗記を集中するとともに、
「攻め」る対象として意識する。
6.送り札
1. 相手の攻撃を分散し、あるいは鈍らせるとともに、自分が相手陣に攻め入りやすくする。
2. 決まり字が短いものから送る。原則として3字決まり、4字決まり、5字決まり、6字決まりは送らない。
◆ポイント1:共札を分ける、「む、す、め、ふ、さ、ほ、せ」、単体の「う、つ、し、も、ゆ」、または相手が感じている札、
的にしている札など。
◆ポイント2:相手と自分を見比べて第1音が同じ札の枚数に差がある場合、バランスをとる。
この場合、相手陣を攻めやすくすることを考えれば、決まり字が短いものから送ることが基本。
(具体例:「みかき」、「みち」、「みよ」で相手に「み」札がない場合、「みよ」もしくは「みち」から送る。)
◆序盤は、次の送り札の候補を3枚程度考えておく(取ってから考えていてはダメ)。
◆「む、め、も」、「さ、し、す、せ」、「つ、ち」、「ふ、ほ」の札は、共札と考えた方がよい。
(自分がそのように思わなくても、対戦相手はそのように思っていることが多い。)
◆(ポイント1、2とも)対戦相手とのバランスを考えながら送る。
(一方的に送り込みすぎると、かえって自分が取りにくくなる。)
◆自分が一方的に押している試合では、相手が守りにくく、かつ、少し自陣を攻めさせるような札の送りと配置を考える
(自分が相手陣を攻めやすくする意味で)。
◆最後に自陣に残す1枚は、1字決まりになるように考えて送る
(1−1になった場合でも、キッチリ守ることが出来るようにするため)。
7.試合運び
1)試合の組み立て
(1)序盤戦
◆“早く取る”というよりも、どちらかと言えば「抜け札」がないように心がける。
◆第1音のみならず、決まり字にもアクセントをつけて覚える。
(2)中盤戦その1(勝っている場合)
◆徐々に相手陣へ攻め込む。徐々に暗記のアクセントを決まり字から第1音に移す。
(3)中盤戦その2(負けている場合)
◆自陣に暗記の比重を置く。
◆抜け札がないように心がける。(“取る”というよりも“拾う”意識)
◆お手付きをしない。(ここでお手付きをすると、相手を勢いづかせ一気に体勢は決する。)
◆相手陣の分れ札はキッチリ取れるように注意しておく(挽回のチャンスの札)。
(4)終盤戦(双方10枚を切って、拮抗している場合)
◆(最初はかなり難しいが)“取る札”、“相手にあげる札”、“拾う札”程度に分け、
札の配置とシミュレーション(取る動き)を考える。
※場にある札を全部取ろうと思っても取れない。この段階では、定位置は関係ない。
2)お手付き
◆序盤のお手付きは十分に挽回可能なので、あまり気にすることはない。
◆終盤(特に10枚を切った段階)では、多くの場合“致命傷”になるのでやらないように心がける。
◆不幸にしてお手付きをしてしまった場合、気を取り直し、次の1枚に集中する。
(次の1枚を取れば、差し引き1枚差だが、取られると一気に3枚差となる。)
3)試合の流れ
◆同じクラスで試合をしている以上、どんなに押されていても少なくとも1回は自分に“流れ”が来る。
また、どんなに押している試合でも、少なくとも1回は“ピンチ”がある。(出札、お手付き、取り損じ 等)。
その“流れ”をいかにつなぎとめ、“流れ”に乗って大きくしていくか、あるいは、“ピンチ”の時に慌てず、
いかに最小限度にとどめるかが試合運びの重要なポイントのひとつ(最初は難しいが)。
◆相手がお手つきをした直後は、“流れ”に乗るチャンスなので、特に神経を集中させ、取りにいく。
以上
戻る