
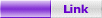 全日本かるた協会
全日本かるた協会
競技かるたでちょっと強くなるための指南書 戻る
2015年2月 武居政敏
2016年8月10日 村上智洋(校正)
Ⅰはじめに
Ⅱ札の配置
Ⅲ暗記
Ⅳ札の送り
Ⅴ戦術
Ⅵお手つき
Ⅶ練習
Ⅷおわりに
Ⅰはじめに
競技かるたに出会って、13年がもう少しでたつ。縁あってはじめ、縁あってA級になり、
縁あってたくさんの出会いや経験をさせていただいた。
少しでもみなさんの競技かるたの競技力向上に役立てていただけたら幸い。
断っておくが、自分の現在のかるたに対する考えや思いをまとめたものである。
つまりこれが絶対でもなく、すべてが間違っているものとも思わない。なるほどと思ったものを取り入れてほしい。
A級には、なれるかるただと思うが、名人/クイーンになれるかるたではないことを一言断っておく。
(ゆうがのかるたは、以下のことをふまえてA級になったと思っているが…)
B級を目指すために ~試合で勝つ可能性を高めるために~
Ⅱ札の配置
入門期と大会にでるようになる人、またB級以上とはちがうかもしれないが、全般的なことを書く。
①相手にとって取りにくい配置(自分にとって取りやすい配置ではない)
・同じ音で始まる札が、左右に分かれること。
・共札は、分けて配置。
・半音も意識して左右に分ける。
例:さ、せ、す、しの、しらは同じ(S音)。か、き、こ(K音)なども意識する。
・大山札は原則右下段(または中段)の外側(囲って取る)
②相手の札配置を見て、必ず定位置から札を動かす
・分れ札は、原則対角に配置(手が交差しないように。表札は確実に取れるように)
・分れ札は、相手との段数をそろえる。または下に配置(相手が下段の場合、自分も下段)
・同じ音で始まる札が相手陣と自陣で縦に並ぶ場合は、なるべく相手より外側に配置。
・左右のバランスを考える(左右の枚数差は5枚以内が理想。それ以上に偏ると枚数が多い側をねらわれやすい)
③一段の長さは、6枚以下が理想
(7枚以上だと決まり字の長さによってはお手つきの可能性が高まる。相手にねらわれる対象になる)
④定位置の決め方
・共札は、左右に分けた定位置が理想。
・1字決まり、うつしもゆ、は原則下段。
・決まり字が長い札(4字、5字)は(囲って取る人と払って取る人とでちがうが)段の外か内。
Ⅲ暗記
15分間のルーティンを決める。強く暗記する札と、あるかどうかだけ確認する札を区別することも大切。
①札の確認(3分)
・「1字決まり、うつしもゆ、いちひき、はやよか、たこみ、おわ、な、あ」の札がどこに何枚あるか確認。
②決まり字を意識して札確認(2分)
・①と同様にする。分れ札の札の取り方を決定(相手陣のみ/自陣のみ/相手陣に行って戻る/自陣から相手陣に行く)
③半音での札確認(2分)
・S音、M音、Y音、K音、T音、H音、その他。
④戦略を考えながら暗記(6分)
・札の色分け(取る札>取りたい札>どちらでも>拾えればラッキー>取られてもよい)の5段階ぐらい。上位3つで35枚ほど。
・上をふまえながら、攻める札、攻める場所、攻める音で戦略をたてる。
・5~8枚、送り札を決める(相手陣が5連続出て、5連取すると仮定して)
⑤並びの確認と戦略の具現化(素振り)(2分)
・段毎に札の確認。
・分れ札、1音による手の動かし方のイメージ化、囲い。
◎試合中の暗記
・札の色分け(取る札、取りたい札)の上位を繰り返し暗記。当然分れ札は暗記。
・移動した札(特に相手陣に送った札)を暗記 → 送った札を取れなければ送った意味がない。
・場にたくさんある音の暗記 → 読まれる可能性が高い。
・自分が空札のときに反応できなかった音の暗記 → 同じ音(同じ札)が読まれた場合を考えて。
Ⅳ札の送り
①共札を分ける
・決まり字が短くなっているものから分ける(もも、もろを両方もっているなど。「うつしもゆ」は最優先)
・決まり字が短いものが複数ある場合、例えば、もも、もろをもち「は」を4枚持っている場合は、「は」を分ける。
・分けた後に決まり字が長くなるものを優先する(大山札→よの→ここ、ちぎ→なに、おお→3字決まり)
・音の偏りがあるものを優先して分ける。
※あさじとあさぼあ、おおえとおおけ、なにしとなにわえ、など3枚で1組の共札のうち2枚を
持っている場合は、共札とみなさない。残りの1枚が読まれ、共札となった場合は送る。
※序盤戦で、かなり有利な状態になった場合(お手つきなどにより)は、共札を分けないこともありえる。
②音の偏りを均一化する(ただし、3字決まり以上は送らない)
・同じ音で始まる札が自陣2枚:相手陣0枚の場合は、自陣1枚:相手陣1枚にする。
同様に、3:0は2:1へ 4:0は2:2まで 3:1は2:2へ 4:1は3:2へ 5:1は3:3まで。
※2:1からの1:2は必ずしも有利になるとはいえない。
※1字決まりの枚数は、同程度がベスト(後半は、相手陣に多くなるように)
③自分の色分け(取る札、取りたい札)のレベルが高い札
④相手の感じの早い札(ねらわれている札)
⑤右下段
⑥取られてもよい札
※1字決まりは、常時1枚はもっておく(運命戦を想定し)
Ⅴ戦術
・25枚差をめざすかるたを取らない。
・5~9枚差。つまり、7~8枚を残して勝つかるたを理想とする。
(結果として、束勝ちになったり2~3枚差になることもあるが)
◎1対1の運命戦は、必ず自陣を守る。(距離の問題が大きい。相手が守れば抜く状況は生まれない)
○序盤/中盤/終盤、勝っている/競っている/負けている、によって取り方を変える。
また、相手の実力の度合いによっても異なる。
(1)試合序盤の戦い方(残数が50~30枚程度)
◎すべての札を取ろうと意識しない(暗記の選択と集中)
◎札の配置を、攻めることによって自分の思い描く方向へもっていく(序盤のポイントは送り札)
・「取る札+取りたい札」を取ることを最優先。その結果として枚数差がつく。
・試合中の暗記は、「取る札+取りたい札」をしっかり暗記(結果として分れ札も)
・2字決まりの札を中心にねらう。また、得意な3字決まり札や、分れ札の一方もねらう。
・大山札の分れは確実に50%でのぞむ。
・送り札は、共札を分けることと音の均一化をめざす。この時点で3字決まりは送らない。
・相手の右下段を1枚は必ず抜く(相手に取れますよというアピールをいれる)、右下段を意識する。
・1字決まりは、1字で取らなくてもよし(意識しすぎない)
・戻り手は必要以上に考えない。
(2)試合中盤の戦い方(残数が30~15枚程度)
◎状況判断を確実にし、それにあわせた柔軟な戦い方の選択。
①有利な状態
○ねらう札(取る札)をしぼり、読まれたときは確実に取る。
・ねらう場所を意識する(大きく分けて、相手の右か左か)
・お手つきを避ける取り方でリスク回避(お手つきが一番だめ。特に3字決まり以上でお手つきしない)
・分れ札は、どちらか一方で(ダブルを絶対にしない)
・相手の右下段を確実にねらう(抜けば抜くほど、相手は自陣に目がいくようになる)
②不利な状態
○自陣を守りながら、攻め込む札をしっかり攻める。
・分れ札をきっちり攻める(相手のダブルをねらう)
・決まり字の長い札を攻める。
・単独音を確実に取る(すべての陣で)
・1字決まりを意識しすぎると他の札がおろそかになるので25%で取れるくらいで暗記する。(4枚あったら1枚は取る)
ただし、1字決まりが多い場合(目安として6枚以上)は50%くらい。
・同音札を相手に固める送りをする(全部送るわけではない)
「あ」の2字決まりなど場全体で残っている音が多い札を送る。つまり1字決まりはあまり送らない。
※暗記が楽になることと、一音目でしっかりと飛び出せるようになることが利点
・3枚のうち2枚を取る気持ちで追い上げる。
・この状況でのお手つきは、そのまま敗北につながる(特に自陣での長い決まりの札を要チェック)
③競っている状態
○最初の戦略通り、特に取り方を変化させるわけではない。
○色分けを変化させながら、戦略も、決まり字の変化に合わせて変えていく。
○流れをつかむ(送り一発をねらう。さける。相手のねらっている札を守る、送るなど)
・差が1~3枚であれば競っている状態と認識する。
・3連取以上されないような意識。
・送り札を3枚程度はいつでもイメージし、イメージどおりの試合展開になるよう心がける。
・自分有利になれば、意識的に相手陣を多くねらう。一音で手を出すイメージ。
・1字決まりの札も意識する。特に相手陣。
(3)試合終盤の戦い方(残数が15~5枚程度)
◎場決まり(読み札2枚、場に2枚、空札なし)の札を強く意識する(勝負の札)。もちろん攻めて取れば、送る札の最重要候補。
◎1字決まりを1字で抜けるように、半音を意識する。1字決まりを積極的にねらう。
◎札の送り、残しにおいても半音を意識した送りをする。(ゆ、よを分ける、ち、つを分けるなど)
◎スピードが上がる分、相手陣の3字決まり以上のお手つきに注意。
◎自陣の3字決まり以上の札を拾う(あくまでねらうのではない)
◎場決まりかつ2字決まりの札は、両方取るように暗記。 → これが終盤でのおおきなポイント。
◎ここでの、攻め方、送り方、お手つきが直接勝敗に結びつく。
◎相手のねらっている札、感じの早い札は送る。
◎札の左右のバランスは意識する。
◎この時点で、札の定位置はあまり意識しない。ただし、自陣で「取る札」に色分けした札は、必ず定位置に置く。
・この時点で、倍セイムの負けている状態になったときは、自陣で減らす意識にかえる。
よって送り札は、決まり字の長い札を送ることもありえる(3字が原則)
※自陣10枚-相手陣5枚。同様に、8-4、6-3、4-2よりわるい状態の場合のこと
(4)最終盤の戦い方(残数が5枚以下)
◎自陣、相手陣に関係なく、取る札、捨てる札を明確に決定する。自分自身の残り枚数分、取る札を設定する。
◎相手が1枚になった時点で(自陣は4枚以下)自陣を100%守る。
札の配置は、1字、2字決まりの札であれば、必ず右下段で守る。
◎上記と逆で、自分が1枚になった有利な状況では、相手陣を囲うくらいの気持ちで強烈に攻める。
ただし、相手が左右に札を分けている場合は、相手は自分の残りの1枚をねらっているということも忘れない。
◎競っている場合は、自陣右下段と相手陣右下段は、同じスピードでは取れないことを意識する。
(どちらか一方に意識を持っていく)読まれるごとにねらう札を替えても可。
Ⅵお手つき
自分自身はお手つきがない試合のほうが少ない。しかし、目安として2回以内が妥当な回数。
それ以上した場合、戦略の建て直しを迫られる場面が多くなる。また、負けているときのかるたをする羽目になり、
不利な状況でかるたを取る確率が高くなるため避けたい。
また、終盤でのお手つきは試合の勝敗と密接な関係をもつ。
場の札が10枚以下になった場合は、お手つきをしないような取り方を考える。(逆に相手にしてもらうような札送りや配置)
自分より格上の人に勝つ場合は、お手つきがない場合であり、格下の人に負ける場合は、お手つきが要因になる場合が多い。
意識することは、お手つきした直後の出札をいかに取るかにかかる。
次読まれた札を取れれば、お手つきはしなかったことと同様である(落ち込む必要はまったくない)
よいお手つきは厳密にはないが、悪いお手つきはある。(基本は暗記の不足によるもの)
①場にない札をさわる
②札を送った後、もとあった場所をさわる
③相手の手の反応速度につられてさわる
以上、3つはさける。
共札の、自陣でのお手つきもさけたい(戻り手もふくむ)
相手陣を攻めての逃げ切れないお手つきであれば、試合展開においてはOKである。(終盤でなければ)
また、半音の聞き分けミスも悪くはない。
Ⅶ練習
練習で必ず練習をする。勝負の勝ち負けではない。勝ち負けを意識するのは、試合直前の練習である。
必ず課題をもって練習すること。
たとえば「相手の右下段は5枚以上抜く」「この札をきれいに抜く」「この音をしっかり聞く」「何枚差で負ける/勝つ」など。
練習の積み重ねで、自分のうまく行かない部分を克服していかなくては強くはなれない。
つまり、勝敗にこだわる練習であれば、苦手な部分はいつまでも苦手なままであり、
同じお手つき、同じ負け方をしていくことになる。
人によって練習時間、機会は様々である。試合数としては、最低年間100試合を目標に。自分自身もこれが基準。
強くなりたければ、やはり年間200試合はしたい。(自分自身は、1年間で200試合以上とった年は、未だにないが…)
素振り等も大切な練習である。特に若い人たちにとっては、フォームを固めることの意義、自分の体の成長に合わせて、
変えなくてはいけないこともある。
ただし、ある程度人生経験がある人にとっては、やりすぎも禁物。筋力との兼ね合いもある気がする。
将棋や囲碁のように、かるたも試合が終わった後にしっかりと感想戦とまではいかないが、相手との対話をしっかりすべきである。
(特に高校生以上の競技者は)これが、強くなる秘訣である。スピードでは、なかなか若い学生等にかなうわけではない。
ならば、戦略で勝つ可能性を高める(勝ち試合を落とさない、負け試合を運命戦まで)
Ⅷおわりに
かるたは楽しいものという根本を忘れてはいけない。負けても楽しい。勝っても楽しい。するのが楽しいのである。
自分自身で苦しくしてはいけない。(くやしいという気持ちはあるが)
強い人と勝負するのは楽しいのです。自分自身も大会では、結果を求めるのでめちゃくちゃ強い人とあたるのは避けたいですが、
あたったときは、自分の現在の実力がどこまで通用するのかを楽しみます。
負けることは前提ですので、相手のこの札は絶対に取ってやろうという気持ちで望みます。それが楽しいのです。
1枚の札をうまく取れたときの喜び。その積み重ねが大切です。
自分自身の目標は、A級で決勝戦に行くことです。まー、後2,3年にできないと目標の変更ですが…。
戻る
